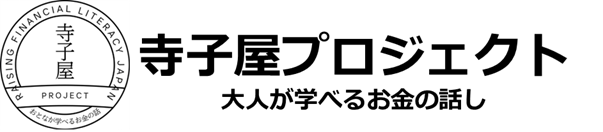メール・電話・SNS…詐欺の手口から自分を守る!第3回:SNS編(投資・なりすまし詐欺)
その2|SNS詐欺の心理と対策編
SNSで狙われる心理と誘導テクニック
SNS詐欺の怖いところは、ただの「うそ」ではなく、心理を巧みに突いてくる点にあります。
信頼をつくる『仕込み』
詐欺師は、最初からお金の話はしません。
まずは「いいね」やコメントで仲良くなり、雑談を続けて心の距離を縮めていきます。
「相談に乗ってくれる人」「味方でいてくれる人」と思わせたところで、
少しずつ投資や副業の話を切り出します。
誘導のテクニック
- 「特別に教える」「あなたなら成功できる」と限定感を出す
- 「今だけ」「あと少しで締め切り」と焦らせる
- 「みんな成功してる」と安心感を与える
- 「失敗しても保証がある」とリスクを薄める
どれも、心理学で言う誘導トークです。
人は信頼している人の言葉や、限定されたチャンスに弱いもの。
詐欺師はその「人間らしい優しさ」や「期待」を利用してきます。
ポイント
「自分は引っかからない」と思っている人ほど危ない。
詐欺師は「疑いにくい人」を選んで近づいてきます。
被害を防ぐための行動チェックリスト
- SNSで「お金」「投資」「副業」の話が出たらまず疑う
- DM・コメントでの金銭や投資に関する誘いには絶対反応しない(安易に返信・個人情報を送らない)
- 不審なリンク・アプリは開かない・入れない
- 認証マークは公式サイトと照合して確認
- 怪しいDMはスクショ→通報→ブロック
- 入金・送金してしまったらすぐに警察・消費者センターへ
最近の摘発例(2025年10月)
- 東大阪市:SNS型投資詐欺で50代女性が530万円被害、外国人グループを逮捕
- 山形県:SNSを通じて70代男性が9,500万円をだまし取られる
- 大分県:「だまされたふり作戦」で現金受け取り役を逮捕

こうした事件が、今も全国で相次いでいます。
「私は大丈夫」と思わず、『怪しいと感じたら立ち止まる』ことが最大の防御です。
補足コラム:偽の投資アプリに注意!
最近は、証券会社や投資取引ツールにそっくりの『偽アプリ』を使った詐欺も急増しています。
見た目は本物の証券アプリやFXツールにそっくりで、アプリ内で「あなたは今、利益が出ています!」と架空の取引画面を見せる手口です。
最初は少額を入金させて「利益が出た」と信じ込ませ、次に「もっと増やしましょう」と高額投資を誘導。
最終的に出金ができなくなり、連絡も取れなくなる、というケースが多数報告されています。
見抜くポイント
- ダウンロードリンクが公式ストア(App Store/Google Play)ではない
- アプリの提供者名が公式企業名と異なる
- 不自然に高い利益率・連勝表示
- カスタマーサポートがLINEやTelegramのみで、公式連絡先がない
対策ポイント
「公式アプリかどうか」を必ず確認!
見慣れないリンクや、過剰な権限を求めるアプリはすぐに削除しましょう。
もし誤ってインストールしてしまった場合は、スクリーンショットを残して削除し、
不審な動作があれば消費生活センター(188)やスマホのサポート窓口へ相談を。
すでに『入金や個人情報を送信してしまった場合は、警察(サイバー犯罪相談窓口)』に連絡してください。

これからの詐欺対策と社会の課題
技術が進化するほど、詐欺の手口も巧妙になります。
詐欺師がAIを悪用するなら、AIがその詐欺を見抜く未来もきっと来るはず。
それまでは、「知ること」、そして「共有すること」で、被害を未然に防いでいきましょう。
| テーマ | 今後のポイント |
|---|---|
| AI合成技術の進化 | 生成AIで有名人の顔や声を偽造した『リアル詐欺化』がさらに進んでおり、見抜く技術の重要性が高まる |
| 広告プラットフォームの責任 | Meta/YouTubeなどの企業側の広告審査強化が鍵 |
| 仮想通貨の悪用 | 匿名での送金が追跡を難しくしている |
| 国際的な摘発連携 | 海外拠点を持つ詐欺組織への国際協力が急務 |
現状の課題:多段階誘導スキーム
SNSからLINEやTelegramを経由し、偽の投資アプリへ誘導する手口は、すでに高度に体系化されています。
「複雑化」ではなく「完成された詐欺モデル」として確立しつつあり、
そのため利用者側の『早期の気づき』と『情報共有』がより重要になっています。
まとめ:信じたい気持ちを悪用される前に
SNSは便利で楽しい場所。
でもその裏側では、あなたの「信頼」を狙う人たちが潜んでいます。
「自分だけは大丈夫」と思わず、ほんの少しの警戒が、大きな被害を防ぐ力になります。
情報をうのみにせず、公式サイトで確かめる。
そして、迷ったときはひとりで抱え込まない。
それが、SNS時代を安全に生き抜くいちばんのコツです。
次回予告は「キャッシュレス決済編」
スマホ決済やQRコードを狙う「詐欺の手口」を解説します!