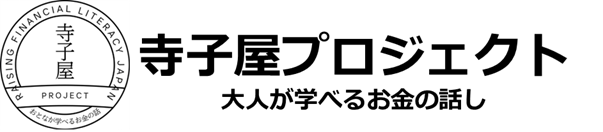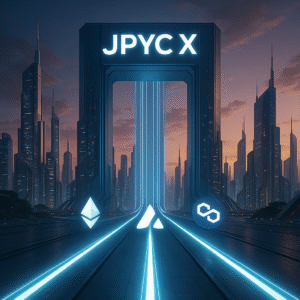【デジタル円】ゆうちょも参加するDCJPYって何?(前編)
「トークン化預金」のしくみと、なぜ今注目されるのか
DCJPYってなに?
最近ニュースで耳にするDCJPY(ディーシージェーピーワイ)。
「デジタル円? 暗号資産?」と思う人もいるかもしれません。
でも実はDCJPYは暗号資産ではなく、銀行預金をデジタル化して使えるようにした『トークン化預金』という仕組みです。
つまり、円の価値をそのまま保ちながらインターネット上で扱える新しい形のお金なのです。
DCJPYの仕組みと特徴
トークン化預金って?
DCJPYの基本は「トークン化預金」。
銀行は、1円の預金に対して1枚のデジタルトークンを発行し、そのトークンをやり取りできるようにします。
つまり利用者が持つのは「銀行預金と1対1で連動するデジタルのお金」です。
これによって、暗号資産のように価格が変動することはなく、常に1円=1 DCJPYの価値が保たれます。
二層構造という特徴
DCJPYは「二層構造」で設計されています。
- 共通領域:銀行が管理する『お金の通り道』。送金や決済を安全に処理する基盤。
- 付加領域:企業が『自動でお金や権利をやり取りできる仕組み(スマートコントラクト)』を組み込み、支払いやポイント連動などを追加できる領域。
2-300x189.jpeg)
たとえるなら、
銀行が作った安全な高速道路(共通領域)の上に、企業がサービスエリアやスマートIC(付加領域)を設置して便利にしていくイメージです。
CBDC(日銀デジタル円)との違い
ここでよく混同されるのが、日銀が検討している『CBDC(中央銀行デジタル通貨)』です。
- CBDC:日銀が直接発行する「公的なお金のデジタル版」
- DCJPY:銀行が自分の預金をデジタル化した「民間のデジタル円」
つまり、DCJPYは「民間主体で動くが、公的な金融インフラともつながっている」仕組みなのです。
また、DCJPYはブロックチェーン技術を活用していて、記録が改ざんできない点も大きな特徴です。
なぜ今注目されているのか
最大の理由は、ゆうちょ銀行の参画です。
2026年度末までに、口座残高を1円=1 DCJPYで交換できる仕組みを導入し、デジタル証券の決済などに活用する計画が報じられています。
さらに背景には、
- キャッシュレス決済の普及
- 海外で進む『デジタルユーロ』構想や、民間主導の『デジタルドル』の動き
- 日本の企業が新しいビジネスモデルを模索している流れ
といった社会全体の動きがあります。
その中で、銀行預金を安全にデジタル化するDCJPYは、日本ならではの選択肢として注目されているのです。
1-300x164.jpeg)
まとめ:DCJPYの基本ポイントと将来の可能性
- DCJPYはトークン化預金:銀行預金を1対1でデジタル化したもので、暗号資産やステーブルコインとは性質が異なる。
- 二層構造で安全性と拡張性を両立:基盤は銀行が守り、その上で企業がサービスを発展させられる。
- ゆうちょ銀行が参加予定:2026年度末までに導入を計画し、実装が近づいている。
現時点では、私たち生活者にすぐ大きなメリットが届くわけではありません。
ただ、裏側の仕組みが変わることで、便利さがじわじわ生活に広がっていく可能性があります。
例えば、コンサートが中止になったら自動で返金される仕組みや、海外のデジタルサービスに円のまま直接支払える仕組みなどが、DCJPYによって実現できるかもしれません。
次回(後編)は、メリットとデメリット、JPYCとの違い、そして将来の生活にどんな影響があるのかを、分かりやすく解説していきます。