【デジタル円】ゆうちょも参加するDCJPYって何?(後編)
前回の記事では、ゆうちょ銀行も参加しているデジタル通貨フォーラムが基盤となるDCJPYが「銀行預金をデジタル化したトークン化預金」であることを解説しました。
つまり、『暗号資産ではなく、銀行預金と1対1で連動するデジタルな円』です。これは、銀行にある預金をトークン化してブロックチェーン上で扱えるようにしたもの、と表現するのが正確です。
今回は、このDCJPYが私たちの生活にどう関わるのか、メリットとデメリット、そしてJPYCなど他のデジタル通貨との違いを見ていきましょう。
DCJPYが期待される理由
生活者にとって
- 即時返金やスムーズな支払い
例:コンサートが中止になったら自動的に返金される、といった仕組みが実現する可能性があります。 - 安心感
DCJPYは銀行の預金が裏付けなので、常に1円=1 DCJPYとして利用できる点が魅力です。(ただし円そのものの価値は為替市場で変動します)
企業にとって
- 送金・決済の効率化
銀行間の送金は現状でもかなり高速ですが、DCJPYの二層構造を利用することで、お金と契約を同じ仕組みで同時に処理できるなど、従来の口座振替にはなかった新しい自動化や同時決済が可能になります。特に企業間の大口取引や自動決済で効率化が期待されています。 - 自動化(スマートコントラクト)
取引条件を満たせば自動で支払いが行われるため、事務コストやリスクを減らすことができます。
DCJPYに残る課題
- ネットや電気に依存
停電や通信障害のときには使えない可能性がある。 - プライバシーとデータ管理
取引履歴がデジタルで残るため、どこまで情報が共有されるのかが課題。DCJPYはプライバシーに配慮した設計を目指していますが、中央集権的な仕組みである以上、誰がどの情報を参照できるのかというルール作りが重要になります。 - 既存キャッシュレスとのバランス
DCJPYはあくまでも銀行預金をデジタル化した仕組みで、現金の代わりになるわけではありません。今後は銀行口座を『デジタルウォレット』のように使う形で、既存のキャッシュレスと併存していくことになりそうです。
DCJPYと現金の違いを整理してみましょう。
- 現金(キャッシュ):紙幣や硬貨として手渡しでき、オフラインでも利用可能。
- 電子決済(PayPayやSuicaなど):特定の事業者が発行する残高で、その枠の中だけで利用可能。
- DCJPY:銀行預金を裏付けに発行されるデジタル円。専用の「デジタル通貨口座」や「ウォレット」を通じて利用する仕組み。
つまり、DCJPYは「現金のデジタル版」というよりも、銀行預金を新しい形で使えるようにしたものです。現金と同じようにオフラインで持ち歩けるわけではなく、銀行システムをベースに動く点が大きな違いです。
JPYCや海外通貨との違い
| 項目 | DCJPY(トークン化預金) | JPYC(電子決済手段) | 海外ステーブルコイン(例:USDT) |
|---|---|---|---|
| 発行主体 | 民間銀行 | 民間企業 | 海外企業 |
| 裏付け資産 | 銀行預金 | 日本円や日本の短期国債 | 米ドルなど |
| 利用範囲 | 銀行を介した国内利用が中心 | ブロックチェーン上で自由 | 世界中(ただし日本では制限あり) |
| 信用性 | 高い(銀行預金と同じ) | 法律で認められた電子決済手段(前払式支払手段として保護) | 流動性は高いが透明性に課題あり |
DCJPYが描く未来のユースケース
DCJPYのホワイトペーパー(Currency Digital DCJPY White Paper 2023)では、将来的にこんな活用例が描かれています。
- 地域のカフェや小売での「手ぶら決済」
地域農家とつながり、食材のトレーサビリティを活かして地元経済を活性化する仕組み。 - アートやクリエイターのNFT取引
DCJPYで作品を売買し、二次流通でも自動的にクリエイターへ報酬が還元される仕組み。 - 環境や社会貢献とつながる経済圏
フードロス削減やカーボンクレジットをDCJPYで取引し、持続可能な消費行動を後押し。
これらはあくまで未来のユースケースですが、「単なる決済手段を超えて社会課題の解決につながる可能性」 を示しています。
そして、将来的に海外のデジタル通貨とも接続できれば、さらに大きな広がりが期待できるでしょう。

DCJPYは、銀行預金をデジタル化して安全に使えるようにした「日本型のデジタル円」です。
メリットは大きいものの、災害時のリスクやプライバシーの問題など、課題もあります。
これからは便利さとリスクの両方を理解して備えることが大切になっていきます。
「デジタル円」が当たり前に使われる時代を想像しながら、これからの変化を一緒に考えていきましょう。
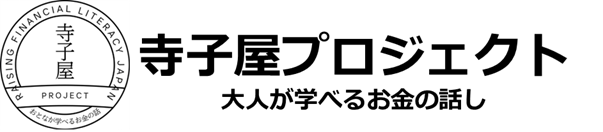
3-300x164.jpeg)
