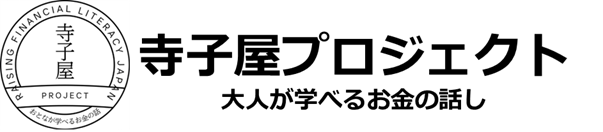仮想通貨の誕生(ビットコインってなに?)_前編
現代と未来のお金シリーズ|第2回
突如あらわれた『インターネットのお金』
2009年、「ビットコイン」という新しいタイプのお金が、世界に向けてひっそりと登場しました。発表したのは正体不明の個人もしくはグループで、「サトシ・ナカモト」という名前で知られています。いまだに正体は不明で、これもまたビットコインのミステリアスな魅力の一つです。
ビットコインは、紙幣や硬貨のような「形」がありません。銀行や国の管理を受けず、インターネット上でやり取りできる「デジタル通貨」です。
ビットコインの目的は?
サトシ・ナカモトが目指したのは、「銀行を通さずに世界中の人が直接お金をやり取りできる仕組み」。たとえば、AさんがBさんに送金する時、これまでなら銀行や決済サービスが仲介していました。でもビットコインなら、インターネットを通じて直接送れるのです。
2-300x300.png)
この仕組みによって、
- 海外送金の手数料や時間を大幅に減らせる
- 銀行口座を持たない人でもスマホやPCがあればお金を受け取れる
というメリットが生まれます。
ビットコインを支える「ブロックチェーン」
ビットコインの取引は、ブロックチェーンという技術によって記録・管理されます。ブロックチェーンとは、取引履歴(台帳)を鎖のようにつなぎ、世界中のコンピュータに分散して保管する仕組み。
これにより、
- 改ざんがほぼ不可能
- 管理者がいなくてもシステムが動く
- 透明性が高い という特徴があります。
誰が発行しているの?
ビットコインには中央銀行がありません。新しいビットコインは「マイニング(採掘)」と呼ばれる作業によって生まれます。金鉱を掘るように、複雑な計算(採掘)を世界中のコンピュータが競い合って行い、最初に成功した人が報酬として新しいビットコインを受け取ります。
発行量はあらかじめ2,100万枚と決められており、無限に増えることはありません。
半減期ってなに?
ビットコインは、約4年ごとに新しい発行量が半分になります。これを『半減期(Halving)』といいます。半減期があることで、ビットコインの供給スピードはどんどん遅くなり、希少価値が保たれる仕組みです。
直近では2024年に半減期があり、発行ペースがさらに減りました。このタイミングでは価格が動きやすいと言われ、投資家の注目イベントにもなっています。
世界で最初の「ビットコインで買い物」
最初の「ビットコインで買い物」として有名なのが、2010年の「ピザ2枚」の取引です。アメリカ・フロリダのラズロ・ハニエツさんが掲示板で「1万BTCと引き換えにピザを買ってくれる人」を募集しました。当時のビットコインに、ピザ屋が対応しているわけがありません。そこで、イギリスの青年が代わりにピザを注文し、法定通貨で支払いました。青年は、そのお礼としてハニエツさんから1万BTCを受け取りました。
4-300x300.png)
当時の1万BTCの価値はわずか4,000円ほどでしたが、これがビットコインが現実世界の商品と交換された、記念すべき第一歩となったのです。
ビットコインのここがすごい
- 世界中どこにでも、スピーディに送金できる
- 国や銀行に依存しない
- 発行量が限られている(インフレしにくい)
- ブロックチェーンで安全性が高い
一方で、
- 価格の変動が大きい
- 送金に数分から数時間かかることがある
- ハッキングや詐欺に注意が必要 といった課題もあります。
新しい動き
近年、ビットコインは「投機の対象」から「資産の一つ」へと見方が変わりつつあります。2024年には米国でビットコイン現物ETFが承認され、証券口座からビットコインに投資できるようになりました。
これはビットコインが世界の金融の一部として認められ始めた大きな出来事です。この話は、次回の「世界とつながるビットコイン」で詳しく紹介します。
ビットコインは、2009年の誕生からわずか十数年で、世界経済に影響を与える存在になりました。その裏側には、銀行に頼らない送金の仕組みや、限られた発行枚数というユニークなルールがあります。
次回は、このビットコインが世界にどう受け入れられ、投資や技術としてどんな未来を描いているのかを見ていきます。