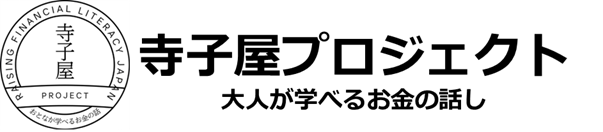株式市場の歴史的な事件とその影響
株式と企業の歴史|番外編
株式市場では、時に想像を超えるような「事件」が起きてきました。
その多くは、単なる経済の話にとどまらず、社会や人々の暮らし方までも変えてきたものばかりです。
この番外編では、日本と世界で起こった「株式市場の大事件」を振り返りながら、そこから得られる教訓を一緒に考えてみましょう。
ブラック・マンデー(1987年)1日で22%下落した衝撃
1987年10月19日、ニューヨーク市場で株価が大暴落。 1日でダウ平均株価が22.6%も下がるという前代未聞の出来事でした。
原因は、プログラム売買(コンピューターによる自動売買)の連鎖でした。 一定の条件で自動的に売買される仕組みが、連鎖的な売りを加速させたのです。
この事件をきっかけに、株価の急変動を抑える「サーキットブレーカー制度」が導入されました。
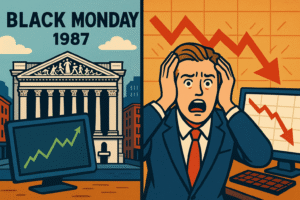
この出来事からわかるのは… テクノロジーは便利だけど、「想定外の動き」を生むこともあるということ。 自動化が進んでも、人の判断がますます重要になる場面があるんですね。
バブル経済崩壊(1990年代)『失われた時代』のはじまり
1980年代後半、日本はまさに「バブル景気」の真っただ中にありました。 土地や株の価格が異常なほどに上昇し、企業も個人も銀行からどんどんお金を借りて投資。 まるで「永遠に景気が良くなる」ような錯覚に包まれていました。
そのお金は、不動産や株式だけでなく、海外にも向かいます。 有名なところでは、ロックフェラーセンターやコロンビア・ピクチャーズ、MCA(ユニバーサル・ピクチャーズの親会社)なども日本の企業が買収し話題となりました。
しかし1990年、金融引き締めによりバブルは崩壊。 株価と地価は暴落し、多くの人が資産を失いました。 ここから始まる「失われた10年」が、日本経済に長く影を落とすことになります。
この出来事からわかるのは… 過熱した市場には冷静な視点が必要ということ。 「みんなが買ってるから自分も」という空気に流されず、本質を見極める目を持つことが大切なんですね。
ITバブル崩壊(2000年代)『夢』が過熱しすぎたとき
1990年代後半、インターネットの普及とともに「ITは未来を変える」という期待が高まりました。 IT関連企業の株価は急上昇し、中には業績がまだ出ていない企業の株まで買われるように。
「とにかくITなら伸びる」と思われた時代でした。
しかし2000年を迎えるとバブルは崩壊。 株価は急落し、多くのIT企業が倒産。 多くの投資家が大きな損失を抱えることになりました。
この出来事からわかるのは… 「夢や期待」だけでは投資は成り立たないということ。 成長性だけでなく、企業の実態や収益力にも注目する視点が必要になるんですね。
リーマン・ショック(2008年)世界が震えた金融危機
アメリカの大手投資銀行「リーマン・ブラザーズ」が破綻したことで起きた、世界的な金融危機。 その波は日本にも押し寄せました。
原因は、「サブプライムローン」という信用力の低い人向けの住宅ローンが金融商品として世界中に広がっていたため、一つの破綻がドミノ倒しのように世界へ波及しました。
日経平均株価はリーマン破綻から数ヶ月で7,000円台まで急落。 企業の業績悪化や雇用不安など、経済の先行きに不安が広がりました。

この出来事からわかるのは… 世界の市場はつながっているということ。 「遠くのニュース」も、自分の資産や生活に影響を与える可能性があることを意識しておきたいですね。
東日本大震災と株式市場(2011年)
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、日本に甚大な被害をもたらしました。 インフラの崩壊や原発事故の影響もあり、経済活動も大きく停滞。
株式市場もすぐに反応し、震災直後は日経平均が一時1,000円以上下落しました。 しかしその後、復興需要や日本企業の回復力への期待から、徐々に持ち直していきます。
この出来事からわかるのは… 市場は「感情」で動く場面もあるということ。 でも一時的な混乱があっても、長期的には回復の兆しが見えることもあります。 焦らず、冷静に見つめる目が大切です。
歴史は“未来のヒント”になる
どんな事件も、当時の人にとっては「まさか」が起きた瞬間でした。
でも振り返ってみると、そこには過熱、過信、過小評価など、人間の感情や行動のクセが見えてきます。
投資に絶対はありません。 でも「過去を知っているかどうか」で、未来への判断が変わることはきっとあるはずです。
今回の「歴史の事件簿」が、みなさんの投資に少しでも役立てばうれしいです。