メール・電話・SNS…詐欺の手口から自分を守る!【第1回】SMS・メール編(フィッシング詐欺)
寺子屋ブログではこれまでも何度かフィッシング詐欺やなりすまし詐欺について取り上げてきました。
でも最近の詐欺はどんどん巧妙になっていて、知識がないと「あれ?本物かな?」と迷ってしまうことも増えています。
特に今話題になっているのが 「国勢調査」を装った詐欺。国勢調査は日本にとって極めて重要な調査であり、国民の義務でもあります。その信頼性を悪用した詐欺が横行しているのです。
今回はこの最新事例を切り口に、SMSやメールを使ったフィッシング詐欺の手口と対策を分かりやすく解説します。
国勢調査を装った詐欺に注意!
国勢調査は公費で運営され、調査員が金銭を請求することは一切ありません。しかしその権威を利用して、偽物が市民を騙そうとしています。
メール・SMS型の詐欺
- 本物そっくりのロゴや文面で「国勢調査にご協力ください」とリンクをクリックさせる。
- 「回答しないと罰則があります」などと書かれていて、不安をあおる。
- 「回答者には記念品を進呈」といった、国勢調査には本来一切存在しない内容を盛り込むケースもあります。
本物との違いはここをチェック!
- 2025年の国勢調査のURLは総務省のサイトに記載されています。
(総務省国勢調査サイト https://www.kokusei2025.go.jp/)
必ず「go.jp」ドメインで提供されますが、不審なURLを受け取った場合は必ず公式サイトなどで確認しましょう。 - 国や自治体がメールやSMSで「直接リンク」を送ってくることはありません。
- 国勢調査には「記念品」や「報酬」はありません。
- メール文面の日本語表現に違和感(不自然な敬語や誤字脱字、句読点の位置)にも注意。
- 差出人名と送信元アドレスが一致しているかも確認しましょう。
訪問型の詐欺
メールだけでなく、調査員を装って家を訪問するケースもあります。
- 個人情報や金融情報を聞き出す。
- 調査票回収を口実に現金を求める。
本物の調査員はここが違う!
- 必ず 「調査員証」 を携帯しています。
- さらに「国勢調査2025」と書かれた 青い手提げ袋 を持っています。
- 回答は「オンライン(e-kokusei.go.jp)」または「郵送」が基本。
- 調査員が現金を求めることは絶対にありません。国勢調査の費用はすべて公費で賄われているため、金銭要求はすべて詐欺です。
1-300x226.png)
(出典:総務省 国勢調査2025公式サイト[注意喚起ページ] https://www.kokusei2025.go.jp/caution/)
ほかにもある!身近なフィッシング詐欺
国勢調査以外にも、私たちの身近に多くのフィッシング詐欺が潜んでいます。
宅配業者を名乗る不在通知
「荷物をお預かりしています」「再配達はこちら」というSMSでリンクを踏ませる手口。
クリックすると偽サイトに誘導され、氏名・住所・クレジットカード番号などを入力させられます。
忙しい時ほど「つい押してしまう」ので注意が必要です。
大手企業・銀行を装うメール
「あなたのアカウントが停止されました」「不正利用が確認されました」など、緊急性を強調するのが特徴。
偽のログインページを開かせ、IDやパスワードを盗み取ります。
本物そっくりに作られているため、メールの送信元ドメインや公式サイトからの情報確認が欠かせません。
サブスクサービス詐欺
「Apple IDがロックされています」「Netflixの利用が停止されます」など、焦りを誘う通知。
ユーザーの焦りにつけ込み、偽サイトでログイン情報を奪われるケースが増えています。
慌てず、アプリや公式サイトから直接ログインすればすぐ真偽が分かります。
騙されないためのチェックリスト
- 不審なリンクは絶対にクリックしない。
- 公式アプリやブックマークからアクセスする。
- 「緊急」「停止」「罰則」「記念品進呈」などのクリックを誘導する言葉に要注意。
- メールの送信元やURLドメインを必ず確認。
- 訪問時は「調査員証」と「国勢調査2025の青い手提げ袋」を確認。現金要求は即アウト。
2-300x183.png)
アカウント乗っ取りを防ぐ最強の盾
多要素認証(MFA)を設定しましょう。
特に認証アプリやパスキーといったフィッシングに強い認証方法の利用を強く推奨します。
万が一被害にあったら
どんなに気を付けていても、うっかりクリックしてしまうことはあります。大事なのは「被害を最小限にすること」です。
- リンクをクリックしただけで入力していない場合
→ サイトを閉じれば基本的に問題ありません。焦らず落ち着いて行動しましょう。 - ID・パスワード・クレジットカード番号などを入力してしまった場合
→ すぐにパスワードを変更してください。
→ クレジットカードを入力してしまった場合はカード会社に連絡して停止手続きを。
→ 可能であれば警察の「サイバー犯罪相談窓口」や消費生活センター(188)にも相談しましょう。 - 参考になる公式窓口
→ フィッシング対策協議会の「緊急情報ページ」では最新の詐欺事例と対処法が公開されています。
まとめ
国勢調査のように「行政を装う」詐欺は、メールやSMS、電話や訪問でも発生しています。
大切なのは「まず疑う」「確認する」を習慣にすることです。
対応を始める前に、必ず家族や信頼できる身近な人へ相談するか、自治体の窓口や警察に電話で確認しましょう。
一人で判断しないことが、最強の防御策です。
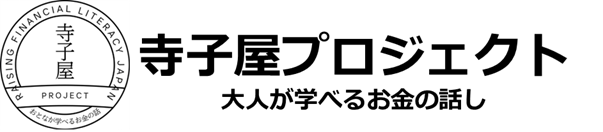

1-300x187.png)