メール・電話・SNS…詐欺の手口から自分を守る!第2回:電話編
国際電話・自動音声・ビデオ通話・特殊詐欺
「電話」は昔から詐欺に使われてきた古典的なツールですが、今でも進化し続けています。
国際電話の料金請求を目的とした詐欺(いわゆる「国際ワン切り」)、自動音声ガイダンス、さらにはビデオ通話を悪用した手口まで登場。
加えて、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった「特殊詐欺(組織的詐欺)」も形を変えてまだ存在しています。
突然かかってきた電話にどう反応すればいいか?
その答えを、具体的な事例と対策でまとめました。
国際ワン切り詐欺
「一瞬だけ着信して切れる→つい折り返す」ことで国際電話の高額な通話料金の請求につながる手口です。
犯人は海外の高額な情報料などが設定された番号を利用しており、かけ直すと通話時間が伸びるほど高額な料金が発生します。
対策
- 知らない海外番号には絶対折り返さない。
- キャリアの「国際電話拒否」設定を有効にする。
自動音声ガイダンス詐欺
「銀行です」「警察です」と名乗り、自動音声で不安をあおるタイプ。
最近はこれに加えて、携帯電話会社や宅配業者を名乗るケースも増えています。
「料金未払い」「不正利用がありました」「再配達ができません」などと言って番号を押させ、情報を聞き出す偽オペレーターにつなぎ、金銭をだまし取ろうとするのが共通のパターンです。
対策
- 自動音声で個人情報や番号を入力しない。
- 不安なら「自分で調べた正規の電話番号」にかけ直す。
サポート詐欺(偽の警告画面)
PCやスマホに「ウイルス感染しました!」と突然表示され、画面に書かれた番号に電話させる手口です。電話するとサポート料を請求されたり、遠隔操作ソフトを入れさせられる危険があります。
ポイント
警告画面自体にウイルス性はなく、電話をかけなければ実害はありません。落ち着いて消すだけで大丈夫です。
正しい対処法(安心ステップ)
- 画面を操作しない:電話番号には絶対かけない。警告音はミュートでOK。
- ブラウザを閉じる:タブやアプリを閉じる。閉じられない場合は、PCならタスクマネージャー、スマホならアプリ履歴から強制終了。
- 電源を切る:強制終了や通常操作で画面が消えない場合は、お使いの機種の強制終了方法で端末の電源を切ってください。
2-300x200.png)
- 念のため、スマホやPCに身に覚えのないアプリやソフトが入っていないか確認しておくと安心です。
ビデオ通話型のなりすまし詐欺
LINEやWhatsAppで、警察官や役所の職員を装ってビデオ通話をしてくるケースも増えています。
警察署の写真などをバーチャル背景に映し出したり、制服を着て「本物らしさ」を演出し、個人情報や金銭を引き出そうとします。
対策
- 公的機関が突然ビデオ通話をしてくることはありません。
- 少しでも怪しいと思ったらすぐ切断。
- 必要なら公式の電話番号に自分で確認を。
まだ残る「特殊詐欺」
古くからある手口も形を変えて続いています。
オレオレ詐欺
「○○だけど…」「携帯が壊れたから新しい番号で」などと家族を名乗る。
最近は分業化が進み、犯人を特定しづらくなっています。
対策:一度電話を切って、家族の普段使っている番号にかけ直して確認する。
還付金詐欺
「○○市役所(年金事務所)の○○です」と名乗り、ATMやコンビニ端末の操作を指示。
「手続きのため」と言いながら、実際は振込をさせる手口です。
対策:公的機関が電話でATM操作を指示することは絶対にありません。即切って確認を。
預貯金詐欺
「あなたの口座が犯罪に使われた」と警察官や銀行協会職員を名乗り、カードを回収に来る。
偽封筒でカードをすり替えるなど巧妙な方法も使います。
対策:カードや通帳を自宅に回収に来ることはありません。金融機関などの窓口に自分で確認を。
騙されないためのチェックリスト
- 知らない番号は出ない、折り返さない。
- 自動音声で「銀行」「警察」「携帯会社」などを名乗る電話は詐欺を疑う。
- PCやスマホの警告画面に書かれた番号に電話をかけない。
- ビデオ通話で制服姿や身分証などを見せられても信用しない。
- 公的機関や企業が、電話でATMの操作やコンビニで売られている プリペイドカード(電子マネー)の購入 を指示するのは100%詐欺です。
- 家族との「合言葉」を決めておくと安心です。
3-300x187.png)
万が一被害にあったら
- 電話で個人情報を伝えてしまった → すぐにパスワード変更、銀行に連絡。
- 金銭を渡した/振り込んだ → 警察(#9110)や消費生活センター(188)に相談。
- カードや通帳を渡してしまった → 金融機関に連絡して利用停止を。
まとめ
電話詐欺は「古典的だけど進化している」手口です。
知らない番号や不自然な連絡には反応せず、落ち着いて本当に必要かどうかを確かめることが何よりの防御策です。
あなた自身の冷静な判断が、一番の安心につながります。
次回はSNS編(投資・なりすまし詐欺)。AIや有名人を悪用した新手の罠を解説します。
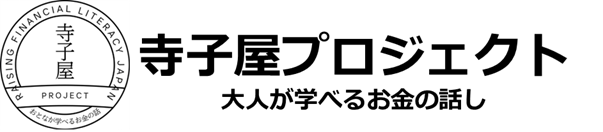
4-300x300.png)
