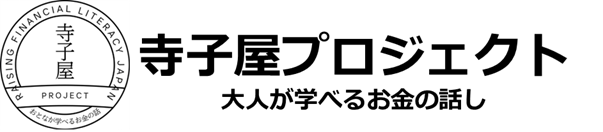メール・電話・SNS…詐欺の手口から自分を守る!第4回:キャッシュレス決済編
その1|便利の裏に潜む罠 キャッシュレス詐欺の最新手口
スマホひとつで支払いができる、キャッシュレスの時代。
コンビニでもカフェでも、財布を出さなくてもOK。
とても便利になりましたよね。
でも、その「便利さ」に目をつけたのが、詐欺師たちです。
最近は、QRコードや非接触決済、ポイント連携など――
新しい仕組みを悪用する「デジタル詐欺」が増えています。
この記事では、いま実際に広がっている詐欺の手口と、「どう見抜けばいいか」をわかりやすく紹介します。
QRコードをすり替える「偽QR詐欺」
かつて実際に起きた手口のひとつに、お店や公共スペースのQRコードをこっそり貼り替える「偽QR詐欺」があります。たとえば2024年には、集合住宅のポストに「家賃支払い用」と偽ったチラシを投函し、QRコードから偽サイトへ誘導する詐欺が報じられました(TBS NEWS DIG)。
また、スーパーや飲食店などのポスターに貼られた偽QRコードを読み取ると不正サイトへ誘導されるケースも確認されています(ITmedia 2023年11月報道)。
このような貼り替え型の詐欺は、以前ほど頻繁には報じられていないものの、今も一定数の被害が確認されている手口です。詐欺師たちは、目立ちにくい形へと手口を変化させながら、私たちの「日常の油断」を狙っています。
QRコードを使うときは、『本物かどうか』を確認する習慣が大切です。
少しでも違和感を覚えたら、スタッフや公式アプリで再確認を。
便利さの裏にあるリスクを意識するだけで、防げる被害は確実に減らせます。
イベントやキャンペーンを装う「便乗型QR詐欺」
「有名アーティストの限定ライブチケットが当たる!」
「いまだけ50%OFF!」そんな言葉に注意です。
人気イベントやキャンペーンをかたって、
偽のQRコードや決済リンクを送りつける詐欺も確認されています。
SNS上で『公式風』のアカウントが偽キャンペーンを拡散し、リンクから不正サイトに誘導するケースもあり、油断はできません。

対策のコツ
あまりにも「お得すぎる話」は、まず疑うこと。
気になるときは、公式サイトで同じキャンペーンがあるか確認してみましょう。
非接触決済を狙う「スキミング」と「スマホ乗っ取り」
カードやスマホをかざすだけで支払える「タッチ決済」。
この便利な仕組みも、悪用されるリスクが指摘されています。
スキミングといえば、昔からある「磁気ストライプ型」の手口が有名でした。
ATMやレジのカード差し込み口に小さな機器を仕掛けて、カード情報を読み取る、そんな古典的な詐欺ですね。
しかし現在では、『非接触型や近距離通信(NFC)を利用した新しいスキミング』の存在が確認されています。
財布の中に入れたままでも数センチの距離から読み取れる機器が出回り、海外では被害報告も出ています。
日本では大きな被害は少ないものの、理論上は情報を盗み取られるリスクがあります。
実際、カード会社各社や金融機関もスキミング被害への警戒を強めています。
SMBCカードは2025年に「非接触型カードでもスキミングの可能性がある」と公式サイトで解説し、防止グッズの利用を推奨。
全国銀行協会も「磁気データを盗んで偽造キャッシュカードを作成する被害が報告されている」と注意喚起を出しています。
つまり、「スキミング=昔の話」ではなく、今も形を変えて残るリスクということ。
非接触決済やICカードの普及によって、見えないところで狙われる可能性があると意識しましょう。
さらに、スマホにウイルスを入れて遠隔操作し、
登録済みの決済アプリを勝手に使うケースも報告されています。
予防法
- 電波を遮断するカードケースを使う
- アプリやOSを常に最新にしておく
- 公式ストア以外のアプリは絶対に入れない
- 利用通知(プッシュ通知・メール通知)をオンにして、不審な決済をすぐ確認できるようにする
アカウント乗っ取りと「パスワード使い回し」の危険
「他のサイトと同じパスワードを使い回している」
これも実は、詐欺師が狙うスキだらけの状態です。
流出したIDとパスワードを使って、
キャッシュレス決済アカウントにログインされる「乗っ取り」被害が今も発生しています。
最近では、『パスワードを使わずに生体認証でログインできる「パスキー(Passkey)」』という新しい仕組みも普及が進んでいます。
これを使えば、フィッシングサイトにパスワードを入力するリスクを根本的に減らせます。
守る方法
- サービスごとに違うパスワードを設定する
- 「二段階認証(2FA)」を必ずオンにする
- パスキー対応サービスでは積極的に利用する
- SMS認証だけでなく、アプリや生体認証を組み合わせる
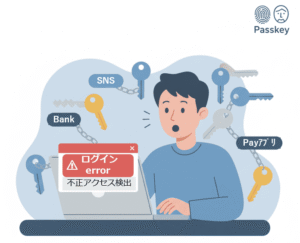
「ポイントがもらえる!」を装う連携詐欺
「今なら1万円分のポイントがもらえる」「○○Payと連携すれば現金還元」などと誘って、偽サイトでアカウント連携を求めるケースがあります。連携を許可すると、詐欺者があなたの個人情報・決済情報を手に入れてしまうことも。
実際に起きている例(日本)
全国銀行協会は、「身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金」の事例を注意喚起していて、詐欺師が不正にアカウントを作成して銀行口座と連携し、預金を不正に引き出す被害が複数報告されていると公表しています。
この事例からわかるのは、あなたが実際にそのキャッシュレスアプリを使っていなくても、銀行口座情報との連携を勝手にされてしまう可能性があるということ。連携機能は便利な反面、リスクにもつながるっています。
回避するコツ
- 正規のアプリストア(App Store/Google Play)で提供されている公式アプリだけを使う
- アプリ内での連携要求は、運営会社名や提供元を確認
- SNSやメッセージで送られてきた「アプリ連携リンク」は開かない
- 「高還元」「限定」「すぐに」など、焦らせる言葉は疑ってみよう
- 連携要求が来たら、①アプリ提供元(開発者名)と②連携先サービス名を必ず確認する
「便利さ」と「安心」はセットで使う時代
キャッシュレス決済は、もはや私たちの生活に欠かせません。
でも、どんなにシステムが進化しても、「使う人の注意」がなければ安全は守れません。
「ちょっと怪しい」と思ったら、一度スマホを置いて深呼吸。
そのひと呼吸が、あなたのお金を守る一番の防御です。
後編では、すぐに実践できる「詐欺に負けないための防御習慣」を紹介します。
安心してキャッシュレスを使いこなすための具体的なコツを、わかりやすくまとめます。