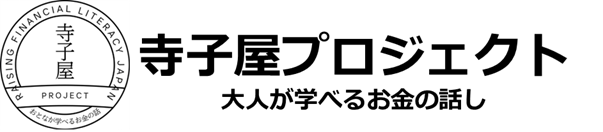日本円がデジタルになって何が変わるの?
円建てステーブルコインJPYC|前編
最近、日本で初めて「円と同じ価値を持つステーブルコイン」が金融庁から正式に認められました。その名も 『JPYC』。
発行は2025年秋に予定されており、いよいよ日本円のデジタル化が現実のものになろうとしています。
このJPYCって一体なんなのか?
あなたの生活にどう関わっていくのか?
そして、現状ではどんな課題があるのか?
このブログでは、JPYCについて3回にわたって分かりやすくお話ししていきます。
デジタルマネーはもう日常
いまや「デジタルなお金」はすでに当たり前になっています。
PayPayやSuica、クレジットカードを使って、私たちは現金に触れずに買い物ができます。
ただし、この「デジタルのお金」には大きな制限があるんです。
PayPayの残高をSuicaで使えませんし、Suicaに入っているお金をPayPayに送ることもできません。
つまり、それぞれのサービスの「枠」に閉じ込められているんです。

日本円そのものをデジタル化すると?
ではもし「現金の日本円そのもの」を、インターネット上で自由にやりとりできる形に変えたら?
それを実現しようとしているのが JPYC です。
JPYCは、1 JPYC = 1円 の価値を常に保つように設計された「日本円のデジタル版」。
SuicaやPayPayと似ているようで、決定的に違うのは、ブロックチェーン(分散型台帳技術)の上で動く という点です。
これにより、特定の企業やサービスに縛られず、誰とでも日本円をやりとりできるようになります。
ちなみに、この仕組みを支えているのが ブロックチェーン です。
ブロックチェーンとは、取引の記録を「みんなで共有する台帳」に書き込む仕組みのこと。
誰か一人が勝手に書き換えられないようになっているため、信頼性が高く、安全にお金をやりとりできるのです。
JPYCで広がる新しい可能性
JPYCが広がれば、私たちの生活はこんなふうに変わるかもしれません。
- 日本円のまま海外送金
銀行を通さなくても、直接日本円を送金できる。
従来は「数日+高い手数料」がかかっていた海外送金が、より安く、速くなる可能性があります。

- オンラインでの直接決済
海外のECサイトやデジタルサービスでも、日本円でそのまま支払える未来。
クレジットカードの為替手数料や国際ブランドの制限を気にせず使えるかもしれません。 - ゲームやデジタルコンテンツ
NFTやゲーム内アイテムを、日本円のまま購入できる。
これまでは暗号資産に両替してから買う必要がありましたが、その手間がなくなります。 - 小売業や個人事業主の負担軽減
クレジットカード決済では加盟店手数料が3〜5%かかりますが、JPYCならもっと低コストでの決済が期待できます。
小さなお店やフリーランスにとっては大きなメリットになるかもしれません。
現状では難しい課題もある
もちろん、JPYCには課題もあります。
- 送金手数料の問題
ブロックチェーンを使う以上、処理のための「手数料(ガス代)」が発生します。
現金やクレジットカードのように「ユーザーが手数料を意識せずに使える仕組み」と比べると、まだハードルがあります。 - 処理スピードの問題
ブロックチェーンは記録を分散して確認する仕組みのため、取引完了までに時間がかかります。
「カフェでコーヒーを買う」ような即時決済にはまだ向いていません。
そのため、当面は「時間がかかっても問題のない送金やオンライン決済」から普及していくと考えられます。 - 現金の強さ
現金には「手数料がゼロ」「すぐに受け渡しできる」という強みがあるため、JPYCがすぐに完全に置き換えることは難しいでしょう。

JPYCは「日本円そのものをデジタル化したお金」。
国際送金やオンライン決済、小規模店舗のコスト削減など、多くの可能性を秘めています。
ただし、現状では「送金手数料」や「処理スピード」といった課題も残されており、すぐに日常の小売決済に広がるわけではありません。
それでも、日本円をインターネットで直接使えるという新しい価値は、お金の未来を大きく変えるかもしれません。
次回は、JPYCとドル建てステーブルコインUSDTの違いを見ながら、さらに深く「デジタルマネーの世界」を掘り下げていきます。