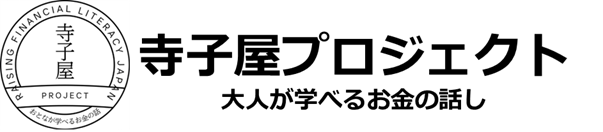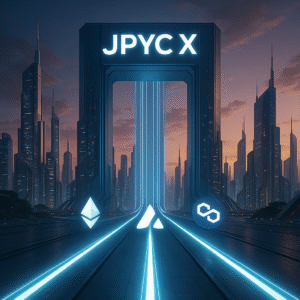日本円ステーブルコイン「JPYC」が、USDTと違う理由
円建てステーブルコインJPYC|中編
前回の記事では、日本円をデジタル化した新しいお金「JPYC」が、私たちの生活をどう便利に変えるかについてお話ししました。
今回はさらに一歩進んで、世界で最も使われているステーブルコイン「 USDT(テザー)」 と比べてみたいと思います。
どちらも「法定通貨と同じ価値を持つように設計されたコイン」ですが、実は大きな違いがあるのです。
ステーブルコインとは?
まず簡単におさらいです。
ステーブルコインとは、ドルや円などの法定通貨の価値に連動させることで、価格の変動を抑えた暗号資産のことです。
例えば、
- USDT(テザー)は、1枚がほぼ1ドルの価値になるように設計されています。
- JPYCは、1枚が常に1円の価値を持つように作られています。
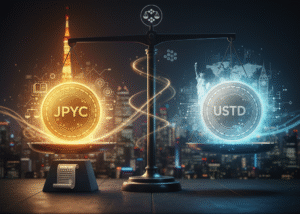
暗号資産は便利だけど、ビットコインのように値動きが激しいと日常の決済には使いにくい。そこで「安定した価値を持つコイン」としてステーブルコインが生まれました。
なお、日本の資金決済法では、円建てのステーブルコインは「暗号資産」とは区別されていて、「電子決済手段」として規定されています。
国ごとに扱いは違いますが、日本ではこうした法的整理がされている点も覚えておくと良いでしょう。
JPYCの特徴
日本円に連動するステーブルコインとして注目されるのが JPYC です。
- 金融庁承認:日本国内で初めて正式に認められたステーブルコイン
- 資金移動業者登録企業:法律に基づいて運営されるため安心感がある
- 1 JPYC = 1円を保証:円と同じ価値を保ち、日本国内で使いやすい
- JPYC Xプラットフォーム:発行・償還手数料を当面無料にするなど、普及を意識した仕組みが用意されている
日本円をそのままインターネット上でやりとりできる「安心感」が最大の魅力です。
USDTの特徴
一方で、世界最大のステーブルコインが USDT(テザー) です。
- 世界中で流通:暗号資産の取引量はビットコイン以上
- 1 USDT = 1ドル:ドルと価値が連動しているため、グローバルで使いやすい
- 発行主体は海外企業(テザー社):規制の枠組みは国ごとに異なる
- 課題もある:担保の透明性や規制リスクへの懸念が常に指摘されている
つまり、同じ「ステーブルコイン」でも、JPYCは日本で電子決済手段として位置づけられているのに対し、USDTは一般的に暗号資産の一種として扱われることが多いのです。
それでも、圧倒的な「流動性」と「自由度」があるため、世界中の暗号資産取引やDeFiサービスで使われ続けています。
現在のJPYCとUSDTの違い(比較)
| 項目 | JPYC | USDT |
| 通貨 | 日本円建て | 米ドル建て |
| 管理 | 金融庁承認、資金移動業者登録企業 | 海外企業(テザー社) |
| 利用範囲 | 日本国内が中心 | 世界中 |
| 信頼性 | 高い(規制に守られる) | 一部懸念あり |
| 自由度 | 限定的 | 高い |
視覚的に整理すると、両者の立ち位置がはっきり見えてきますね。
トレードオフ(信頼性 vs 自由度)
ここで重要なのが「トレードオフ」の視点です。
- JPYC:日本の規制に守られ、安心して利用できる。ただし、現状では利用範囲は国内が中心で、自由度は限られる。
- USDT:世界中で使える自由度と利便性がある。ただし、規制リスクや担保の不透明さという課題を抱える。
つまり「どちらが優れているか」という話ではなく、使う目的やシーンによって選び方が変わるのです。
安心と自由、その先に待つ未来へ
JPYCは「日本ならではの安心感」、USDTは「世界で使える利便性」。
両者の違いを理解すると、自分がどんな場面でどちらを選ぶべきかが見えてきます。
次回は、JPYCが金融庁に承認されたことで、日本のWeb3などのビジネスにどんな影響を与えるのかを考えていきます。